
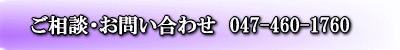
| 〜葬儀用語解説〜 葬儀の用語は多々あります。 仏教用語が使われていても…という言葉 仏教とは本来関係のないにも関わらず…という言葉 仏教とは全く関係のない…地域の風習や俗習、迷信から出来た言葉 葬儀社が“商品”として名称付けた言葉 など様々です。 これらをある程度ピックアップしご説明させて頂きます。 今まで当たり前に行っていた行為や発言が実は… 故人、親族を冒涜していた 一部の地域の人を差別していた ほんとは恐ろしい行為だった という事もあります。 |
+後祓い
葬儀に出席した者に、死者の霊魂が憑依しないよう、死の穢れを祓い清める事。
これは故人や親族への冒涜行為である。
清めの塩を体に撒く、水(酒)で手を洗う、灰を撒く、藁を燃やし燻す(叩く)などの行為のこと。地域によって様々な事を行う。
仏教伝来前の葬送の殯(モガリ)や、神式の祓徐(後祓)の儀、食品の保存加工工程が元になっており…
・ 神道では「神が死を嫌う」
・ 殯では「穢れた人ほど腐敗していく」
・ 保存加工では手の殺菌に酒を使う。料理に塩漬け、燻製がある。あく抜きを“灰汁抜き”と書くように灰を使い行っている。
昔は洗濯や歯磨きに灰を使っていた。日本酒が病気(火落ち)になった際、灰で殺菌消毒していた。
これらが結びつき、出来たものだと考えられる。
なお、仏教では死は穢れではなく、神道の本宗の神社本庁では、「清めに塩は使わない」と公示されたため、塩を使う理由も目的も一切なく、現在の清め塩は、宗教性のないただの因習となっている。
また、江戸期は火葬を行うのは「穢多非人」の仕事とされ、「その者達の穢れを落とす」という、人種差別、部落差別の行為から生まれたともされており、、現在では行ってはいけない事である。
これは故人や親族への冒涜行為である。
清めの塩を体に撒く、水(酒)で手を洗う、灰を撒く、藁を燃やし燻す(叩く)などの行為のこと。地域によって様々な事を行う。
仏教伝来前の葬送の殯(モガリ)や、神式の祓徐(後祓)の儀、食品の保存加工工程が元になっており…
・ 神道では「神が死を嫌う」
・ 殯では「穢れた人ほど腐敗していく」
・ 保存加工では手の殺菌に酒を使う。料理に塩漬け、燻製がある。あく抜きを“灰汁抜き”と書くように灰を使い行っている。
昔は洗濯や歯磨きに灰を使っていた。日本酒が病気(火落ち)になった際、灰で殺菌消毒していた。
これらが結びつき、出来たものだと考えられる。
なお、仏教では死は穢れではなく、神道の本宗の神社本庁では、「清めに塩は使わない」と公示されたため、塩を使う理由も目的も一切なく、現在の清め塩は、宗教性のないただの因習となっている。
また、江戸期は火葬を行うのは「穢多非人」の仕事とされ、「その者達の穢れを落とす」という、人種差別、部落差別の行為から生まれたともされており、、現在では行ってはいけない事である。
+位号
戒名の(「〜〜院−− ○○」の○○の部分)に付けられる位を指す文字の事。性別(士・女)、年齢(童や子)、功徳報恩により低位から高位のものとなる(各宗派による)
院号とは違い、位号は、各宗派の戒律を守る事を約束した(戒律を守った)者が授かるものであり、現代の「居士は○○万円、信士は△△万円」と、いうのは大きな矛盾である。
これが罷り通るのであれば、まさに「地獄の沙汰も金次第」となってしまう。
律宗と真宗系では、位号は用いない。地域、時代によっては用いられていたこともあるが、宗門では認められていない。
院号とは違い、位号は、各宗派の戒律を守る事を約束した(戒律を守った)者が授かるものであり、現代の「居士は○○万円、信士は△△万円」と、いうのは大きな矛盾である。
これが罷り通るのであれば、まさに「地獄の沙汰も金次第」となってしまう。
律宗と真宗系では、位号は用いない。地域、時代によっては用いられていたこともあるが、宗門では認められていない。
+位牌
中国から仏教が伝来した際に、中国の「霊の依代」という習俗と、仏教の卒塔婆が習合したものと考えられており、中国の儒教の葬礼品の霊牌(死者の官位と姓名を書いた板)と同一視され位牌という名称が使われている。
鎌倉期に禅宗と共に伝わったとされている。江戸期の檀家制度と共に一般化された。
位牌の上部書かれる文字は、宗派により異なる。
真宗系では、高田派を除き、位牌ではなく過去帳を用いる。
戦国期、江戸期に反一向宗姿勢をとっていた大名家の影響もあり、それらの地域では真宗門徒である事を隠すためなどもあり、位牌を用いる地域もあるが、正式なものではない。
鎌倉期に禅宗と共に伝わったとされている。江戸期の檀家制度と共に一般化された。
位牌の上部書かれる文字は、宗派により異なる。
真宗系では、高田派を除き、位牌ではなく過去帳を用いる。
戦国期、江戸期に反一向宗姿勢をとっていた大名家の影響もあり、それらの地域では真宗門徒である事を隠すためなどもあり、位牌を用いる地域もあるが、正式なものではない。
+院号
元々は、皇族が住む邸宅を院と呼び、隠居し○○院上皇と呼ばれた事に由来。(嵯峨天皇→嵯峨院 冷泉天皇→冷泉院など)
貴族が仏教の戒律を守ることが出来ない為、寺院を建立し、○○院家(持明院家など)、○○寺家(徳大寺家など)となった。
僧侶も院号を持つ僧侶は少なくない。院号は寺院を建立した者や、天皇から送られた者、現代で宗派側が追号として贈られたものなどが多い。
太平洋戦争で戦没者には無条件で院号を付けることとなり、現在のように院号が普及した。
現在では、生前に寺院や宗派に多大な貢献をした者、社会的地位の高い者に贈られる。
注意点としては、院号は○○寺に貢献した事により贈られたものであり、寺院を変える、改宗した場合は使えない。
貴族が仏教の戒律を守ることが出来ない為、寺院を建立し、○○院家(持明院家など)、○○寺家(徳大寺家など)となった。
僧侶も院号を持つ僧侶は少なくない。院号は寺院を建立した者や、天皇から送られた者、現代で宗派側が追号として贈られたものなどが多い。
太平洋戦争で戦没者には無条件で院号を付けることとなり、現在のように院号が普及した。
現在では、生前に寺院や宗派に多大な貢献をした者、社会的地位の高い者に贈られる。
注意点としては、院号は○○寺に貢献した事により贈られたものであり、寺院を変える、改宗した場合は使えない。
+院殿号
元々は武家の院号の代わりであり、位としては院号の下である。
足利尊氏の戒名が「等持院殿…」である事から始まる。
院号が皇族以外の貴族にも用いられるようになった事と、院殿号は幕府の将軍職や大大名のみが用いてきた事による希少性などから、院号よりも院殿号が位が上と思われている。
現在では、大臣職に就いた政治家などに用いられている。
本来、仏教の教えからは遠く離れたものである。
足利尊氏の戒名が「等持院殿…」である事から始まる。
院号が皇族以外の貴族にも用いられるようになった事と、院殿号は幕府の将軍職や大大名のみが用いてきた事による希少性などから、院号よりも院殿号が位が上と思われている。
現在では、大臣職に就いた政治家などに用いられている。
本来、仏教の教えからは遠く離れたものである。
+永代供養
永代供養とは本来、○○家が末代まで先祖を弔う事であり、寺院が永久的に供養をする事ではない。
江戸期の檀家制度に伴い、檀家の少ない寺院が一周忌、三回忌…と少額ずつの御布施をまとめて「○回忌までの分」として受け取った事が始まり。
墓地の広告にある“永代供養墓”は○○家永代の墓を指し、永遠に一個人をお寺と霊園業者が供養することはない。
墓地を相続する後継者がいない場合は当然撤去される。霊園業者が倒産した場合も同じ。
または、10・30・50回忌までの○○年分の管理費などが初期費用に含まれており「○○回忌までは面倒を見るがそれ以降は合葬墓」というものである。
真宗系では故人は阿弥陀如来のお力でお浄土に生まれているため、遺族が故人を弔う事はしない。
永代に渡り浄土真宗の御教えと共に生き、御教えを伝える」事を“永代教”という。
法事も弔うのではなく、法事を縁とし仏法に触れる事、いのちの無常を知る事である。
永代教と永代供養は全くの別物である。
江戸期の檀家制度に伴い、檀家の少ない寺院が一周忌、三回忌…と少額ずつの御布施をまとめて「○回忌までの分」として受け取った事が始まり。
墓地の広告にある“永代供養墓”は○○家永代の墓を指し、永遠に一個人をお寺と霊園業者が供養することはない。
墓地を相続する後継者がいない場合は当然撤去される。霊園業者が倒産した場合も同じ。
または、10・30・50回忌までの○○年分の管理費などが初期費用に含まれており「○○回忌までは面倒を見るがそれ以降は合葬墓」というものである。
真宗系では故人は阿弥陀如来のお力でお浄土に生まれているため、遺族が故人を弔う事はしない。
永代に渡り浄土真宗の御教えと共に生き、御教えを伝える」事を“永代教”という。
法事も弔うのではなく、法事を縁とし仏法に触れる事、いのちの無常を知る事である。
永代教と永代供養は全くの別物である。
+御斎
法座、法要の時に出される料理の事。
精進料理で酒も飲まない。
御斎は本来、不殺生(ふせっしょう)という。
戒律を守った寺院での食事であり精進料理の原型で、命を奪わず、命を生むもの(米や豆などの種)も食べることはしない。(現在の精進料理は平安期の公家の料理から出来た物で不殺生よりもかなり緩い)
日本では、農民がそれぞれ収穫した野菜を供物とし、法座、法要に寺院へ行き、その供物を使い寺院で食事を取った事が現在の御斎につながる。
通夜の食事は、遺族を葬儀にだけ集中させるため、村が総出で役割分担し、煮物やおにぎりなどを作り持ち寄り、遺族や会葬者を出迎えていた。現在はその名残が逆転したもの。
精進料理で酒も飲まない。
御斎は本来、不殺生(ふせっしょう)という。
戒律を守った寺院での食事であり精進料理の原型で、命を奪わず、命を生むもの(米や豆などの種)も食べることはしない。(現在の精進料理は平安期の公家の料理から出来た物で不殺生よりもかなり緩い)
日本では、農民がそれぞれ収穫した野菜を供物とし、法座、法要に寺院へ行き、その供物を使い寺院で食事を取った事が現在の御斎につながる。
通夜の食事は、遺族を葬儀にだけ集中させるため、村が総出で役割分担し、煮物やおにぎりなどを作り持ち寄り、遺族や会葬者を出迎えていた。現在はその名残が逆転したもの。
+御布施
布施には…
財施・・・・金銭、食事、衣服を施す 法施(・・・仏法を説く 他に無畏施、和顔施、言辞施などがある
寺院の考えを除き、御布施=財施というのが一般的である。
浄土真宗系と他宗派では布施の考え方に大きな違いがある。
浄土真宗系では仏法を聞くための場である寺院を維持するための財施である。
葬儀、法事も故人に説くものでなく、会葬者に説くもので法施である。
このため、読経料、法名料の概念は通常の寺院にはない。
禅宗系の布施とは修業を積むことに代わる信仰心の表れであり、少額の場合「信仰心の無い檀家」になりかねない。
一般的な“布施”に含まれないものとしては
戒名料・・・戒名の代金 院号料・・・院号の代金 読経料・・・読経してもらう事への謝礼
御車代・・・会場への交通費 御膳料・・・食事につかなかった時の食事代 など
財施・・・・金銭、食事、衣服を施す 法施(・・・仏法を説く 他に無畏施、和顔施、言辞施などがある
寺院の考えを除き、御布施=財施というのが一般的である。
浄土真宗系と他宗派では布施の考え方に大きな違いがある。
浄土真宗系では仏法を聞くための場である寺院を維持するための財施である。
葬儀、法事も故人に説くものでなく、会葬者に説くもので法施である。
このため、読経料、法名料の概念は通常の寺院にはない。
禅宗系の布施とは修業を積むことに代わる信仰心の表れであり、少額の場合「信仰心の無い檀家」になりかねない。
一般的な“布施”に含まれないものとしては
戒名料・・・戒名の代金 院号料・・・院号の代金 読経料・・・読経してもらう事への謝礼
御車代・・・会場への交通費 御膳料・・・食事につかなかった時の食事代 など
か行
+戒名
院号 道号 戒名 位号
○○院 ◇◇ △△ 居士 の△△の部分の事。
仏門に入り授戒を受けた者が、戒律を守る証として授かる名のこと。
現在では死後にお金で買うものになっているが、本来、仏教とは死後の宗教ではなく、生きるための宗教である。
戒名は生前に授かるものである。
戒名を用いない宗派としては
浄土真宗(真宗十派)は法名で釋○○である。
日蓮宗系は日蓮正宗を除き法号を用いる
○○院 ◇◇ △△ 居士 の△△の部分の事。
仏門に入り授戒を受けた者が、戒律を守る証として授かる名のこと。
現在では死後にお金で買うものになっているが、本来、仏教とは死後の宗教ではなく、生きるための宗教である。
戒名は生前に授かるものである。
戒名を用いない宗派としては
浄土真宗(真宗十派)は法名で釋○○である。
日蓮宗系は日蓮正宗を除き法号を用いる
+陰膳(蔭膳)
昔、武士が戦に出張る(遠征や出征))際、戦場や行軍中に食料に困ることの無いように供えた。おまじないや呪術の名残である。
食事の際、本人が座っていた場所や、床の間、神棚の前に置かれていた。供えた後、家族で食べる。
これらが“死出の旅”(三途の川などを越え)無事に閻魔大王のもとに辿り着くように…と変化した。
本来は必要な物ではない。そのうえ殆どの陰膳は手を付けられる事なく廃棄される(いのちを捨てている)。
宗派によるが、閻魔大王の裁きがあるのであれば、陰膳を理由に地獄行きになりうる。
真宗系では用いない。
食事の際、本人が座っていた場所や、床の間、神棚の前に置かれていた。供えた後、家族で食べる。
これらが“死出の旅”(三途の川などを越え)無事に閻魔大王のもとに辿り着くように…と変化した。
本来は必要な物ではない。そのうえ殆どの陰膳は手を付けられる事なく廃棄される(いのちを捨てている)。
宗派によるが、閻魔大王の裁きがあるのであれば、陰膳を理由に地獄行きになりうる。
真宗系では用いない。
+仮通夜
近年、葬儀に来る寺院などが決まらず、火葬せねばならなくなり「とりあえず寺院なしで…」という通夜を仮通夜と呼ぶがそれは大きな間違いであり、葬儀社が作った用語である。
仮通夜とは、本来、亡くなった当日の夜に親族のみで行う通夜の事で、友人や知人が来る通夜は本通夜と呼ばれる。本通夜が無ければ仮通夜もないため、現在では、一部の地域や、寺族関係者、知名人を除き、ほぼ行われることはない。
仮通夜とは、本来、亡くなった当日の夜に親族のみで行う通夜の事で、友人や知人が来る通夜は本通夜と呼ばれる。本通夜が無ければ仮通夜もないため、現在では、一部の地域や、寺族関係者、知名人を除き、ほぼ行われることはない。
+忌
現在では、忌中を理由に「故人に対し失礼になるため、挨拶や祭などの祝い事に参加しない期間」とされているが、間違いである。
“忌”とは“己が心”と書き、「縁者が亡くし、己がいのちの儚さを心で知り考える」という事。
生きるという事は、身近な人に支えられ、食事では動植物のいのちと引き換えに栄養としており、新年を迎えられた自分の命は喜ばしい事である。
現在の“忌”の考え方は神道の死の考え方から来ている。
神道では死を穢れとし神が嫌うため、「神社の境内、参道は神が通る道であり神への冒涜である事」「祝い事に葬家が来ると場が穢れる」「人が集まる場に葬家が来ると穢れが移る」等とされ避けられてきたことに由来する。
真宗系門徒を除き、江戸期の檀家制度により一般庶民に仏式の葬儀が広まったが、この際に混同され現在の忌中・喪中の因習が生まれた。
“忌”とは“己が心”と書き、「縁者が亡くし、己がいのちの儚さを心で知り考える」という事。
生きるという事は、身近な人に支えられ、食事では動植物のいのちと引き換えに栄養としており、新年を迎えられた自分の命は喜ばしい事である。
現在の“忌”の考え方は神道の死の考え方から来ている。
神道では死を穢れとし神が嫌うため、「神社の境内、参道は神が通る道であり神への冒涜である事」「祝い事に葬家が来ると場が穢れる」「人が集まる場に葬家が来ると穢れが移る」等とされ避けられてきたことに由来する。
真宗系門徒を除き、江戸期の檀家制度により一般庶民に仏式の葬儀が広まったが、この際に混同され現在の忌中・喪中の因習が生まれた。
+忌中払い(忌明け)
忌の説明にあるように、忌を“穢れ”とし、「穢れが無くなるお祝い」の宴会を開く因習。
地域により様々であり、その人から故人の親等により期間が異なる。
3日、5日、一週間、四九日、百か日、一周忌までとあり関係が遠いほど忌中の日数は短い。
見方を変えて考えてみると…
あまり関係の無い人は穢れが少ないから短く、親兄弟は穢れが酷いから一周忌まで…。
自分にとって唯一の親や兄弟が亡くなった瞬間に穢れとされているのである。
そして、穢れが落ちたからパーッと飲んでお祝いしましょう。という親兄弟を冒涜されている事になる。
初七日と四十九日が一般的だが、裁定を下す閻魔大王が現れるのは五十七日とされている。その前に酒を飲むのは不殺生を破る事になる。
真宗系では用いない。
地域により様々であり、その人から故人の親等により期間が異なる。
3日、5日、一週間、四九日、百か日、一周忌までとあり関係が遠いほど忌中の日数は短い。
見方を変えて考えてみると…
あまり関係の無い人は穢れが少ないから短く、親兄弟は穢れが酷いから一周忌まで…。
自分にとって唯一の親や兄弟が亡くなった瞬間に穢れとされているのである。
そして、穢れが落ちたからパーッと飲んでお祝いしましょう。という親兄弟を冒涜されている事になる。
初七日と四十九日が一般的だが、裁定を下す閻魔大王が現れるのは五十七日とされている。その前に酒を飲むのは不殺生を破る事になる。
真宗系では用いない。
+供花(献花)
献花には2つの意味合いがある。
1. 仏教では荘厳に供える花(供花)の事。
本堂や仏壇、葬儀の荘厳、墓に供える。
白い菊のイメージが一般的であるが、菊や樒、ヒバ、などと季節の花が用いられる。
組み方は宗派、法要によって変わる。
バラなどのトゲ(人を傷つける)のある花、香りのの強い花、毒性のある花は用いない。
浄土真宗では常華は用いない。
2. キリスト教葬(告別式)、無宗教葬などで用いられる焼香に代わる行為である。
キリスト教では特に花の種類は決まっていない。神式では榊。無宗教葬は決まりはない。
1. 仏教では荘厳に供える花(供花)の事。
本堂や仏壇、葬儀の荘厳、墓に供える。
白い菊のイメージが一般的であるが、菊や樒、ヒバ、などと季節の花が用いられる。
組み方は宗派、法要によって変わる。
バラなどのトゲ(人を傷つける)のある花、香りのの強い花、毒性のある花は用いない。
浄土真宗では常華は用いない。
2. キリスト教葬(告別式)、無宗教葬などで用いられる焼香に代わる行為である。
キリスト教では特に花の種類は決まっていない。神式では榊。無宗教葬は決まりはない。
+献杯(献盃)
献杯には2種類がある。
1. 祝い事の席などで主賓の者や参加者に敬意を払い盃を合わせず上に向けかざす事。
杯をぶつける行為はお互いがぶつかり合える=対等な立場の者にする行為。
欧州では毒を盛っていない事を証明する下賤な者達がする行為とされ、貴族階級の酒宴では行わない。
こちらが本来の献杯である。
2. 通夜後、火葬中の食事の席で故人を偲び、故人へ向け盃を捧げる事。
故人に捧げるという事は、現在私たちのいる娑婆世界に故人はいる事になる。
それは仏教の世界には存在しない霊や魂と言った類のものである。=成仏していない。彷徨える霊魂になった。
主賓(故人)に向け「杯を捧げるから自分には憑りつかないでくれ」と言う俗習や迷信である。
1. 祝い事の席などで主賓の者や参加者に敬意を払い盃を合わせず上に向けかざす事。
杯をぶつける行為はお互いがぶつかり合える=対等な立場の者にする行為。
欧州では毒を盛っていない事を証明する下賤な者達がする行為とされ、貴族階級の酒宴では行わない。
こちらが本来の献杯である。
2. 通夜後、火葬中の食事の席で故人を偲び、故人へ向け盃を捧げる事。
故人に捧げるという事は、現在私たちのいる娑婆世界に故人はいる事になる。
それは仏教の世界には存在しない霊や魂と言った類のものである。=成仏していない。彷徨える霊魂になった。
主賓(故人)に向け「杯を捧げるから自分には憑りつかないでくれ」と言う俗習や迷信である。
+香奠(香典)
香奠の“奠”は「お供えする」と言う意味があるが、香典の“典”は当て字で意味は持たない為、香奠が正しい。
「仏式の場合、通夜は御霊前で(まだ霊魂である)、告別式は御佛前(成仏された)。薄墨(涙で薄まる。力が入らない)で書き、中身に新札は入れない(用意していない様相に)。これがマナーである」とされているが、当てつけや間違いである。
仏教に霊魂は存在しない為、“御霊前”と書いた場合、故人に対し「成仏できずにさ迷ってください」と言う冒涜になりうるので注意。
仏式の場合、通夜も葬式も御佛前が正しい。他には“御香料”“御香奠”が良い。
神式の場合は御霊前、御玉串(料)、御榊料である。キリスト教は御花料で御ミサ料(御弥撒料)は間違えである。
お札は、“お供えする”事が目的である事から新札が好ましい。(お供物に食べかけの物を供えないのと同じ)
御自宅などに直接、香奠を持って行く場合、仏壇の前にお供えする。(仏壇の中にはお供えしない)
向きは仏壇から見て正面を向け、こちらからは上下反転している向きでお供えする。
「仏式の場合、通夜は御霊前で(まだ霊魂である)、告別式は御佛前(成仏された)。薄墨(涙で薄まる。力が入らない)で書き、中身に新札は入れない(用意していない様相に)。これがマナーである」とされているが、当てつけや間違いである。
仏教に霊魂は存在しない為、“御霊前”と書いた場合、故人に対し「成仏できずにさ迷ってください」と言う冒涜になりうるので注意。
仏式の場合、通夜も葬式も御佛前が正しい。他には“御香料”“御香奠”が良い。
神式の場合は御霊前、御玉串(料)、御榊料である。キリスト教は御花料で御ミサ料(御弥撒料)は間違えである。
お札は、“お供えする”事が目的である事から新札が好ましい。(お供物に食べかけの物を供えないのと同じ)
御自宅などに直接、香奠を持って行く場合、仏壇の前にお供えする。(仏壇の中にはお供えしない)
向きは仏壇から見て正面を向け、こちらからは上下反転している向きでお供えする。
+告別式
葬式の丁寧な言い方とされ、よく使われるが間違えである。
告別式はキリスト教の葬式に当たる。または無宗教葬のお別れ会の事。
テレビや雑誌で“通夜”という言葉は伝わりやすいが、“葬儀”と“葬式”を分別して伝えられない事から広まった。
寺院の住職に「○日が通夜で◎日が告別式…」と言うと、
「お通夜までは僧侶が勤め、葬式は神父さんか牧師さん、または無宗教葬」という事になりうる。
告別式はキリスト教の葬式に当たる。または無宗教葬のお別れ会の事。
テレビや雑誌で“通夜”という言葉は伝わりやすいが、“葬儀”と“葬式”を分別して伝えられない事から広まった。
寺院の住職に「○日が通夜で◎日が告別式…」と言うと、
「お通夜までは僧侶が勤め、葬式は神父さんか牧師さん、または無宗教葬」という事になりうる。
+御本尊
さ行
+祭祀相続
当主が死亡した場合、または隠居などに、より家督を相続した際、それ以降の仏事(または神事)も相続する。相続をしたものが寺院との付き合い、墓地、仏壇などを責任を持って行う。というもの。
家督制度、長子制度の廃止(遺産の平等分配)と共に認識が薄まってきてはいるが、長子が相続するというイメージだけは残っている。
詳しくは、“寺院とのトラブル 祭祀相続”を…
家督制度、長子制度の廃止(遺産の平等分配)と共に認識が薄まってきてはいるが、長子が相続するというイメージだけは残っている。
詳しくは、“寺院とのトラブル 祭祀相続”を…
+斎壇(祭壇)
仏事、神事の法要、催事の際に設ける。
一般的なイメージで斎壇というと“白木の祭壇”になる。しかし、白木の祭壇は仏教には関係が無い。
白木の祭壇の”祭”の字は神式の葬儀「神葬祭」から来ており、「戦時中の戦没者は、靖国神社に魂として帰る」とされ仏式でも白木の祭壇を使うことを半強制化された。
神道では死を穢れとするため神社内では行わず、自宅や集会場などで白木の祭壇を組む。
斎壇の組み方や仏具の安置方法は宗派により異なり、また法要により変わる。
仏教喉の宗派でも共通している点は、御本尊は中央の一番上で他の物と被らないように安置する事である。
一般的なイメージで斎壇というと“白木の祭壇”になる。しかし、白木の祭壇は仏教には関係が無い。
白木の祭壇の”祭”の字は神式の葬儀「神葬祭」から来ており、「戦時中の戦没者は、靖国神社に魂として帰る」とされ仏式でも白木の祭壇を使うことを半強制化された。
神道では死を穢れとするため神社内では行わず、自宅や集会場などで白木の祭壇を組む。
斎壇の組み方や仏具の安置方法は宗派により異なり、また法要により変わる。
仏教喉の宗派でも共通している点は、御本尊は中央の一番上で他の物と被らないように安置する事である。
+死穢
死を穢れとする考え方。仏教では死を「生まれた以上当然の事」であり、穢れではない。
日本に仏教が伝来し広まるまでの葬儀儀礼、殯(もがり)が死穢の考え方の始まり。
死者を棺(現代の形とは違う)、若しくは別棟に仮安置する。時間と共に腐敗、白骨化していく事を目にし、“死”を確認する。
腐敗が細菌などが原因とは理解されておらず、聖人であれば腐敗せず、下賤な行為を働いた者は、ひどく腐臭が漂い腐敗する。とされていた。当然、幾重にも偶然が重ならない限り、腐敗は当然の事であり、「死=穢れ」になった。
日本に仏教が伝来し広まるまでの葬儀儀礼、殯(もがり)が死穢の考え方の始まり。
死者を棺(現代の形とは違う)、若しくは別棟に仮安置する。時間と共に腐敗、白骨化していく事を目にし、“死”を確認する。
腐敗が細菌などが原因とは理解されておらず、聖人であれば腐敗せず、下賤な行為を働いた者は、ひどく腐臭が漂い腐敗する。とされていた。当然、幾重にも偶然が重ならない限り、腐敗は当然の事であり、「死=穢れ」になった。
+数珠・念珠
数珠と念珠はよく同一視されるが、実際は全く別の物である。
数珠は“数”の珠と書くように、真言、念仏を何回唱えたのかを数える(摘まんでいく)為に用いる。
真宗系では念仏を唱えた数は関係が無く、仏前での崇敬の念の表れとし、擦り合わせたり、摘まんで数えたりはしない。
真宗系では“お念珠”である。
また各宗派により、珠の数、梵字の有無、房の形などが違い、掛け(持ち)方も異なる。全宗派共通のものはない。
百貨店などで売られている物は、ただの装飾品ととらえるべきである。店員に聞いても、専門の知識が無く「どの宗派でも大丈夫」といい加減な事を言われるだけである。
購入する場合、所属寺院に相談する事が一番である。
数珠は“数”の珠と書くように、真言、念仏を何回唱えたのかを数える(摘まんでいく)為に用いる。
真宗系では念仏を唱えた数は関係が無く、仏前での崇敬の念の表れとし、擦り合わせたり、摘まんで数えたりはしない。
真宗系では“お念珠”である。
また各宗派により、珠の数、梵字の有無、房の形などが違い、掛け(持ち)方も異なる。全宗派共通のものはない。
百貨店などで売られている物は、ただの装飾品ととらえるべきである。店員に聞いても、専門の知識が無く「どの宗派でも大丈夫」といい加減な事を言われるだけである。
購入する場合、所属寺院に相談する事が一番である。
+初七日〜四十九日法要(中陰)
死亡した日から、数えで7日目に初七日法要が行われる。
古代インドは7進法のため7日毎に法要が行われる。
初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日(四十九日)である。
全宗派、初七日法要の有無、日にちの数え方は同じであるが、法要の意味は異なる。
死後、死者は死出の旅へ出る。その後、四十九日に、浄土へ行くか、六道のどこの世界に生まれ変わるかが決まるとされている。
死の陰(地獄)か陽(浄土)かが決まっていない中間にいるため、この期間を“中陰”と呼ばれている。
生前に功徳を積んでいなかった故人に代わり、親族が法要を勤め、生前の罪を軽くするという意味もある。
真宗系では、臨終と同時に阿弥陀如来の力により浄土に生まれ変わるため、この期間は“いのちをかんがえる”機関である。
真宗系でも中陰という言葉はなぜか使われているが、使う意味はないはずである。
古代インドは7進法のため7日毎に法要が行われる。
初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日(四十九日)である。
全宗派、初七日法要の有無、日にちの数え方は同じであるが、法要の意味は異なる。
死後、死者は死出の旅へ出る。その後、四十九日に、浄土へ行くか、六道のどこの世界に生まれ変わるかが決まるとされている。
死の陰(地獄)か陽(浄土)かが決まっていない中間にいるため、この期間を“中陰”と呼ばれている。
生前に功徳を積んでいなかった故人に代わり、親族が法要を勤め、生前の罪を軽くするという意味もある。
真宗系では、臨終と同時に阿弥陀如来の力により浄土に生まれ変わるため、この期間は“いのちをかんがえる”機関である。
真宗系でも中陰という言葉はなぜか使われているが、使う意味はないはずである。
+施主・喪主
施主は、寺院に依頼した祭祀相続者ととらえるのが一般的で、役所へ提出する書類の届出人とは異なる場合がある。
喪主は、様々な意味合いも持つが、「死穢に関与した者達の筆頭者」と言う神道的な差別的な意味合いの方が強いのである。
一昔前は、親族の代表者は喪主で、葬儀委員長(町内会長などの葬儀の設営者)は施主と分けたのもこの意味合いが強い。
真宗系では喪に服すことはない。三重県の員弁地域は真宗門徒が多く、葬儀の際は赤飯が御斎に出される。
赤飯は「浄土に生まれ変わる喜び」を表しているとされる。
喪主は、様々な意味合いも持つが、「死穢に関与した者達の筆頭者」と言う神道的な差別的な意味合いの方が強いのである。
一昔前は、親族の代表者は喪主で、葬儀委員長(町内会長などの葬儀の設営者)は施主と分けたのもこの意味合いが強い。
真宗系では喪に服すことはない。三重県の員弁地域は真宗門徒が多く、葬儀の際は赤飯が御斎に出される。
赤飯は「浄土に生まれ変わる喜び」を表しているとされる。
た行
+檀家
インドの言葉のダーナバディを壇越と音写し、壇越の家が檀家と略された。意味は寺院や僧侶を援助する者。
日本では、先祖や家系を重んじ崇拝する傾向があり、出来た日本特有の仕組みである。
鎌倉期までは仏教は有力者の限られた者のみが信仰できるものであった。その後、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗により仏教は庶民に広まる。
江戸期にキリシタンを取締る目的で寺請制度により、(浄土真宗の門信徒、日蓮宗の檀信徒は除き)近隣の寺院の檀家になる事を強制された。これにより、僧侶となり修業せねばならない宗派にも、在家信者(一般人の信者)ができ、収入源となった。小さな寺院は収入に悩まされ、これが後に「永代供養」を生み出す。
この制度は、戸籍の管理をすることも兼ねており、臨終時、または当日に枕経(死亡者の本人確認)も広まった。
古い家が多い地域は「通りのこっち側は○○寺、そっちは△△寺」と分けられているのはこのためである。
真宗系では檀家ではなく門徒である。
日本では、先祖や家系を重んじ崇拝する傾向があり、出来た日本特有の仕組みである。
鎌倉期までは仏教は有力者の限られた者のみが信仰できるものであった。その後、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗により仏教は庶民に広まる。
江戸期にキリシタンを取締る目的で寺請制度により、(浄土真宗の門信徒、日蓮宗の檀信徒は除き)近隣の寺院の檀家になる事を強制された。これにより、僧侶となり修業せねばならない宗派にも、在家信者(一般人の信者)ができ、収入源となった。小さな寺院は収入に悩まされ、これが後に「永代供養」を生み出す。
この制度は、戸籍の管理をすることも兼ねており、臨終時、または当日に枕経(死亡者の本人確認)も広まった。
古い家が多い地域は「通りのこっち側は○○寺、そっちは△△寺」と分けられているのはこのためである。
真宗系では檀家ではなく門徒である。
+弔電
何らかの理由により葬儀に会葬できない者が、施主に向け、会葬の断りを入れたもの。
断りの電報を読む必要はない。その上、来てもいない人間の名前を、会葬に来てくれた人の前で挙げる必要は全くない。
弔電の拝読は、バブル期に「こんなにもすごい企業から電報が届いた」という施主側の見栄、会社側の営業手段でもあった。バブル期は知らない人の葬儀でも「参列さえすれば金が入ってくる」という、馬鹿げた行為が横行していた。
断りの電報を読む必要はない。その上、来てもいない人間の名前を、会葬に来てくれた人の前で挙げる必要は全くない。
弔電の拝読は、バブル期に「こんなにもすごい企業から電報が届いた」という施主側の見栄、会社側の営業手段でもあった。バブル期は知らない人の葬儀でも「参列さえすれば金が入ってくる」という、馬鹿げた行為が横行していた。
+通夜
亡くなった当日に、夜通し行われていた。
交通網が発達していない頃、遠方から駆けつける親類、縁者は夜中に着くことが多くかった。
宗家、本家の人が来た際、誰もいないのは無礼であるため、通常、親族のうち1人だけは故人に付きっきりの状態にし交代で休む。
向こう三軒両隣の世帯は、親類、縁者の接待、料理の準備などが行われていた。
これが、言葉と表面上の形だけが残り、現在の“門燈” ”寝ずの番” “通夜振舞(御斎)” “受付”となる。
ちなみに、通夜に参加するのは親類のみであり、一般会葬者は葬式に参加する事が本来はマナーである。
一般の会葬者が、葬式にだけ参加する理由は…
通夜当日は亡くなった当日であり、遺族は心身ともに疲れ果てている事。
親類、縁者の接待にから駆られている事を考え避けた事。
埋葬(土葬時)の手伝いをする為。(現在の出棺時の棺を運ぶ力仕事と墓地での穴掘りである)
交通網が発達していない頃、遠方から駆けつける親類、縁者は夜中に着くことが多くかった。
宗家、本家の人が来た際、誰もいないのは無礼であるため、通常、親族のうち1人だけは故人に付きっきりの状態にし交代で休む。
向こう三軒両隣の世帯は、親類、縁者の接待、料理の準備などが行われていた。
これが、言葉と表面上の形だけが残り、現在の“門燈” ”寝ずの番” “通夜振舞(御斎)” “受付”となる。
ちなみに、通夜に参加するのは親類のみであり、一般会葬者は葬式に参加する事が本来はマナーである。
一般の会葬者が、葬式にだけ参加する理由は…
通夜当日は亡くなった当日であり、遺族は心身ともに疲れ果てている事。
親類、縁者の接待にから駆られている事を考え避けた事。
埋葬(土葬時)の手伝いをする為。(現在の出棺時の棺を運ぶ力仕事と墓地での穴掘りである)
+通夜振舞(御斎)
本来、通夜には親類、縁者のみが参加できるものである。
そして、向こう三軒両隣の家が、「家事などせず葬儀にだけ集中しろ」「泣き続けて食事もしてないんじゃないか?」と遺族に料理を振舞った事と、親類、縁者達の接待に振舞った事が、通夜振舞(御斎)である。
現在では昼間は仕事のため葬式に参加する事が出来ない場合が多いが、上記の理由と、本来は精進料理の事を考えるならば、酒を飲み宴会を(焼香からの流れで式中に))始めるのは、無礼の極みである。
そして、向こう三軒両隣の家が、「家事などせず葬儀にだけ集中しろ」「泣き続けて食事もしてないんじゃないか?」と遺族に料理を振舞った事と、親類、縁者達の接待に振舞った事が、通夜振舞(御斎)である。
現在では昼間は仕事のため葬式に参加する事が出来ない場合が多いが、上記の理由と、本来は精進料理の事を考えるならば、酒を飲み宴会を(焼香からの流れで式中に))始めるのは、無礼の極みである。
+道号
院号 道号 戒名 位号
○○院 ◇◇ △△ 居士 の◇◇の部分の事。
真言宗、天台宗、臨済宗、曹洞宗、浄土宗、日蓮宗などで用いられる。
戒名の目に付けられるもので、由来は諸説あり不明。
道号の文字数は宗派内の功績により異なる。
律宗と真宗系(高田派を除く)では用いない。
高田派は 釋 △△ ○○で△△の部分が道号
「一休さん」で有名な一休宗純は一休が道号で戒名は宗純(宗順)
○○院 ◇◇ △△ 居士 の◇◇の部分の事。
真言宗、天台宗、臨済宗、曹洞宗、浄土宗、日蓮宗などで用いられる。
戒名の目に付けられるもので、由来は諸説あり不明。
道号の文字数は宗派内の功績により異なる。
律宗と真宗系(高田派を除く)では用いない。
高田派は 釋 △△ ○○で△△の部分が道号
「一休さん」で有名な一休宗純は一休が道号で戒名は宗純(宗順)
な行
は行
+仏花(佛華)
仏前に供える花の事。供花
+分骨
一人の遺骨を2つ以上の収骨容器(骨壺)に入れ、埋葬、納骨、保管などをする事。
小さな骨壺に喉仏を入れ、大きな骨壺に他の部位を入れる事が一般的である。
通常、分骨する際は各火葬場で分骨証明書が必要である。分骨器と分骨証明は同じ場所に保管しなければならない。
収骨後、分骨証明がない場合(不要な地域を除く)、勝手には分骨は出来ない。
一度、埋葬した遺骨を分骨する場合は、墓地管理者、墓地利用者(契約者)などが立会いのもと行わなければならない。
これらを行わず、勝手に行う事は、死体損壊罪・死体遺棄罪に当たる。
現在では、墓地を所有しておらず、遺骨の保管に困るケースが多い。その場合、分骨容器に喉仏だけを収容し、残りは処分してもらう事も出来る、各火葬場で残骨処分宣誓(申請)書を提出すれば、可能である。
小さな骨壺に喉仏を入れ、大きな骨壺に他の部位を入れる事が一般的である。
通常、分骨する際は各火葬場で分骨証明書が必要である。分骨器と分骨証明は同じ場所に保管しなければならない。
収骨後、分骨証明がない場合(不要な地域を除く)、勝手には分骨は出来ない。
一度、埋葬した遺骨を分骨する場合は、墓地管理者、墓地利用者(契約者)などが立会いのもと行わなければならない。
これらを行わず、勝手に行う事は、死体損壊罪・死体遺棄罪に当たる。
現在では、墓地を所有しておらず、遺骨の保管に困るケースが多い。その場合、分骨容器に喉仏だけを収容し、残りは処分してもらう事も出来る、各火葬場で残骨処分宣誓(申請)書を提出すれば、可能である。
ま行
+埋葬
一般的には遺骨を墓地、納骨堂などに納骨する事をさす。法的には、法的手続きのもと火葬(土葬など)を行う事を意味する。
一部の地域では、鳥葬、風葬、水葬が行われることがあるが、これらは一部の地域の習慣であり都市部で行う事は認められない。
自宅(保管する場合を除き)などの敷地内に墓地を建て埋葬する事は認められない。
散骨する場合にも同じく、遺骨の大きさ場度に規定があり勝手には行えない。また土地所有者の許可が必要である。散骨は“節度を持って行う限り、違法ではない”
これらに違反すると、死体遺棄罪・死体損壊罪が適用される。また、地域によっては条例違反になる場合もある。他人の土地の場合、勝手に行うと訴訟が起こる。自宅であっても近隣の人から苦情、訴訟の対象にもなりうる。
一部の地域では、鳥葬、風葬、水葬が行われることがあるが、これらは一部の地域の習慣であり都市部で行う事は認められない。
自宅(保管する場合を除き)などの敷地内に墓地を建て埋葬する事は認められない。
散骨する場合にも同じく、遺骨の大きさ場度に規定があり勝手には行えない。また土地所有者の許可が必要である。散骨は“節度を持って行う限り、違法ではない”
これらに違反すると、死体遺棄罪・死体損壊罪が適用される。また、地域によっては条例違反になる場合もある。他人の土地の場合、勝手に行うと訴訟が起こる。自宅であっても近隣の人から苦情、訴訟の対象にもなりうる。
+枕経
江戸期の寺請制度により生まれたものである。
寺院が死亡者の本人確認をするための勤行であった。
真宗系では枕経はない。故人が亡くなる前に僧侶、親族と一緒に行う最後のお勤めを「臨終勤行」と言う。
寺院が死亡者の本人確認をするための勤行であった。
真宗系では枕経はない。故人が亡くなる前に僧侶、親族と一緒に行う最後のお勤めを「臨終勤行」と言う。
+密葬
「家族だけで行う葬儀」とされているが、間違いである。
権力者や有力者の葬儀で行われることが多い。一般会葬者を呼ぶ大規模な葬儀(本葬)は準備に時間が掛かかる。その前に親族、親類のみで行われる葬式の事を密葬と言う。
密葬は親族、親類で行われるため、1人の場合もあれば、200人を超す場合もあり、規模は関係が無い。
火葬は密葬後でも本葬後でも良いが、密葬後に火葬されて本葬を迎える事が多い。。本葬を行わないのであれば密葬とは呼ばない。社葬などは本葬としてとらえられる事もある。
密葬と同じように“仮通夜”も通夜が行わなければ仮通夜ではない。
権力者や有力者の葬儀で行われることが多い。一般会葬者を呼ぶ大規模な葬儀(本葬)は準備に時間が掛かかる。その前に親族、親類のみで行われる葬式の事を密葬と言う。
密葬は親族、親類で行われるため、1人の場合もあれば、200人を超す場合もあり、規模は関係が無い。
火葬は密葬後でも本葬後でも良いが、密葬後に火葬されて本葬を迎える事が多い。。本葬を行わないのであれば密葬とは呼ばない。社葬などは本葬としてとらえられる事もある。
密葬と同じように“仮通夜”も通夜が行わなければ仮通夜ではない。
+喪服
現在、「喪服=黒服」のイメージであるが間違いである。
現在の喪服は、大久保利通の葬儀に黒の大礼服で出席する者が多かった事からの流行である。仏教、神道への関連性はない。
本来の喪服は白が正しい。現在でも一部の地域ではその風習は残っている。
また、現在の喪服は正装ではなく、また礼装でもない。(略礼服として売られているが略礼服でもない)
制服の着用が義務付けられている職業(警察官や消防隊員、自衛官など)は礼装があり、その礼装で構わない。
現在の男性の正装は紋付袴である。和装の正装は時代に合わないため洋装で構わないが、洋装の礼装は燕尾服、略礼服がタキシードであり、こちらも結婚式のイメージがある。
女性の正装は白無垢、打掛、留袖である。女性の正装の礼服は、「黒留袖は葬儀のイメージ」はあるものの白無垢、打掛共に結婚式のイメージが強い。
また、“葬儀のマナー”で耳にする「真珠のネックレスは一連のみ」「革製品は使わない」「光り物は避ける」などについては…。
“真珠”は1つ取るために阿古屋貝を最低でも2匹殺している。形の良い物を集めるには「15匹ほど殺して1つ取れるか?」というものであり、完全に殺生であり、着用は避けるべきである。
流行元は現皇后がクリスチャンであり、結婚当時のミッチーブームから流行した。
“革製品”も真珠と同様で避けるべきだが、洋装の正装やスーツではベルトと革靴でなければならない為、革製品の鞄などを避けるだけで良い。
“光り物を避ける”というのは本来不要である。金銀屏風は慶事に金、弔事に銀を使うが表裏一体で紙一重の表れである。
また、真宗系寺院の本堂は金箔と漆などを使い極楽浄土を表している。避ける必要はないが節度を持って着用すべきである。
現在、間違いだらけの“葬儀のマナー”や葬儀のイメージなどにより、本来の正装はすべて着る事が出来ないのが現状である。
現在の喪服は、大久保利通の葬儀に黒の大礼服で出席する者が多かった事からの流行である。仏教、神道への関連性はない。
本来の喪服は白が正しい。現在でも一部の地域ではその風習は残っている。
また、現在の喪服は正装ではなく、また礼装でもない。(略礼服として売られているが略礼服でもない)
制服の着用が義務付けられている職業(警察官や消防隊員、自衛官など)は礼装があり、その礼装で構わない。
現在の男性の正装は紋付袴である。和装の正装は時代に合わないため洋装で構わないが、洋装の礼装は燕尾服、略礼服がタキシードであり、こちらも結婚式のイメージがある。
女性の正装は白無垢、打掛、留袖である。女性の正装の礼服は、「黒留袖は葬儀のイメージ」はあるものの白無垢、打掛共に結婚式のイメージが強い。
また、“葬儀のマナー”で耳にする「真珠のネックレスは一連のみ」「革製品は使わない」「光り物は避ける」などについては…。
“真珠”は1つ取るために阿古屋貝を最低でも2匹殺している。形の良い物を集めるには「15匹ほど殺して1つ取れるか?」というものであり、完全に殺生であり、着用は避けるべきである。
流行元は現皇后がクリスチャンであり、結婚当時のミッチーブームから流行した。
“革製品”も真珠と同様で避けるべきだが、洋装の正装やスーツではベルトと革靴でなければならない為、革製品の鞄などを避けるだけで良い。
“光り物を避ける”というのは本来不要である。金銀屏風は慶事に金、弔事に銀を使うが表裏一体で紙一重の表れである。
また、真宗系寺院の本堂は金箔と漆などを使い極楽浄土を表している。避ける必要はないが節度を持って着用すべきである。
現在、間違いだらけの“葬儀のマナー”や葬儀のイメージなどにより、本来の正装はすべて着る事が出来ないのが現状である。
+殯(もがり)
仏教伝来以前の日本の古代の葬送儀礼。
歴史は古く魏志倭人伝にはすでに記載されており、大化の改新までの約350年間行われていた。
現在の神道や、民間信仰の元になっているが、あまり知られていない。
死者を棺に入れ(またはそのまま)、専用の建物である殯宮(もがりのみや)を建てそこに安置する。
親族は遺体には近づかず、殯宮の前に作る殯庭(もがりのにわ)と呼ばれる庭で諸儀礼を行う。
諸儀礼の意味は、死者の復活や死者の魂に対する恐れ、魂の慰めである。
そして腐敗が始まり、白骨化していく様子を見る事により、「死」を確認した。
生前の行いが良い者は腐敗せず、腐臭も放たないが、生前の行いが悪い者は腐敗し、酷い腐臭がするとされた。
そして、腐敗の状況は奴隷に近い者が確認に行くが、腐敗による有毒ガスに犯され死亡する事もあった。
その為、親族は近づかない。
(現在でも火葬場、葬儀関係の職に就くものを差別的にみる風習が残っているが、これは江戸期の人種差別である「穢多非人」の者が就いたことに由来する。)
これが「穢れ」「呪い」「差別」「清め」などとなっていくのである。
歴史は古く魏志倭人伝にはすでに記載されており、大化の改新までの約350年間行われていた。
現在の神道や、民間信仰の元になっているが、あまり知られていない。
死者を棺に入れ(またはそのまま)、専用の建物である殯宮(もがりのみや)を建てそこに安置する。
親族は遺体には近づかず、殯宮の前に作る殯庭(もがりのにわ)と呼ばれる庭で諸儀礼を行う。
諸儀礼の意味は、死者の復活や死者の魂に対する恐れ、魂の慰めである。
そして腐敗が始まり、白骨化していく様子を見る事により、「死」を確認した。
生前の行いが良い者は腐敗せず、腐臭も放たないが、生前の行いが悪い者は腐敗し、酷い腐臭がするとされた。
そして、腐敗の状況は奴隷に近い者が確認に行くが、腐敗による有毒ガスに犯され死亡する事もあった。
その為、親族は近づかない。
(現在でも火葬場、葬儀関係の職に就くものを差別的にみる風習が残っているが、これは江戸期の人種差別である「穢多非人」の者が就いたことに由来する。)
これが「穢れ」「呪い」「差別」「清め」などとなっていくのである。
や行
ら行
+六道
天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道うを指す。
人間としての生を終え、解脱(成仏)できなかった者が生まれ変わるとされる。
大きく分けて6つであるが、1つにつき何個もの階層に分れている。
人間道は人間が住む世界で、四苦八苦に悩まされ苦しみが多いが、楽しみもある世界で、唯一自力で仏教に出会う事ができ、解脱し仏になる事が可能だと言われている。このため、人間道から解脱できない者はまた、輪廻を繰り返す事となる。
天道を俗に言う“天国”と思いがちだが間違いである。
六道の中では最上位の世界ではあるが、すぐ下が人間道でありさほどの違いはない。悟りも開いておらず、煩悩からも解放されていない為、天道での生を終えると、閻魔大王に生前の行いにより再び裁かれ輪廻する。
「○○に生まれ変わる」「天国で…」と言うのは、いまだ六道の中にいて「成仏できていない=地獄にもいく」という事になる。
宗派により様々な考え方がある。
真言宗、天台宗では「六道のどの世界でも救われる可能性がある」とされている。(観音信仰)
真宗系では、六道に堕ちる事はない。
人間としての生を終え、解脱(成仏)できなかった者が生まれ変わるとされる。
大きく分けて6つであるが、1つにつき何個もの階層に分れている。
人間道は人間が住む世界で、四苦八苦に悩まされ苦しみが多いが、楽しみもある世界で、唯一自力で仏教に出会う事ができ、解脱し仏になる事が可能だと言われている。このため、人間道から解脱できない者はまた、輪廻を繰り返す事となる。
天道を俗に言う“天国”と思いがちだが間違いである。
六道の中では最上位の世界ではあるが、すぐ下が人間道でありさほどの違いはない。悟りも開いておらず、煩悩からも解放されていない為、天道での生を終えると、閻魔大王に生前の行いにより再び裁かれ輪廻する。
「○○に生まれ変わる」「天国で…」と言うのは、いまだ六道の中にいて「成仏できていない=地獄にもいく」という事になる。
宗派により様々な考え方がある。
真言宗、天台宗では「六道のどの世界でも救われる可能性がある」とされている。(観音信仰)
真宗系では、六道に堕ちる事はない。
+六灯
斎壇の脇に3対ずつ置く明かりである。盆提灯を仏壇の前に3対ずつ置くのも同じである。
六道から来ている事は明らかだが、なぜ六道の「成仏できていない」という事を用いるのかが不明である。
六道から来ている事は明らかだが、なぜ六道の「成仏できていない」という事を用いるのかが不明である。
+輪廻
六道の世界に生まれ変わり続ける事。成仏し浄土に生まれ変われていないこと。
+六文銭
「あの世で金に困らないように」「三途の川の渡し賃」とされている(冥銭)。
「あの世で…」と言うのはただの願望であり必要性はない。
三途の川を超えるために必要とされているが、「舟代なのか」「三途の川で追い剥ぎをする懸衣翁、奪衣婆に払うのか」などは不明である。三途の川を越えたら必要が無いとされている。
冥銭は世界中に見られ、古代ギリシャや古代ローマでは、死者の目に冥銭を置いた。世界中の冥銭はたいてい「この世(此岸)からあの世(彼岸)に渡る為に使う」と言う不思議な共通点を持つ。
現在では金属類は火葬炉に入れられない為、通常は1枚の紙にプリントされた六連銭を使う(稀に木製)。
“三途の川”自体が俗信であり、仏教とは関係が無い。
真宗系では絶対に用いない。
「あの世で…」と言うのはただの願望であり必要性はない。
三途の川を超えるために必要とされているが、「舟代なのか」「三途の川で追い剥ぎをする懸衣翁、奪衣婆に払うのか」などは不明である。三途の川を越えたら必要が無いとされている。
冥銭は世界中に見られ、古代ギリシャや古代ローマでは、死者の目に冥銭を置いた。世界中の冥銭はたいてい「この世(此岸)からあの世(彼岸)に渡る為に使う」と言う不思議な共通点を持つ。
現在では金属類は火葬炉に入れられない為、通常は1枚の紙にプリントされた六連銭を使う(稀に木製)。
“三途の川”自体が俗信であり、仏教とは関係が無い。
真宗系では絶対に用いない。
故人の使っていた茶碗に山盛りのご飯を一杯盛り、箸を立てたもの。箸を1本立てるか2本立てるかは地域により異なる。
白米を山盛りにする理由は、高級な白米を大量に食べることができなかったため、「最後(死亡後)くらい白米を食べさせてあげよう」ということから。白米1合を普段使っているお釜とは別鍋で炊いて作る。
また茶碗1杯だけにする理由は「家を出て再び帰らぬ時は一膳の飯に限る」という習慣があった。嫁入りの際の家族との別れの食事はすべて一膳飯だった。
これは二(フタ)たび家へ帰らぬという意味であるとされる。
箸を立てる理由は「箸が刺さっていれば他の者が食べないから」「線香(大天香に見立て)を立てるから箸も立ててみた」「普段寝かしておく箸を立てる事により、(故人の魂に)死んだと理解させる」など不明。
1本だけ立てる理由も「縦は火、横は水。米は木。椀は土。と五行説から来たともされる。
また、椀の淵に寝かせれば十文字になるため、江戸時代の隠れキリスト教徒が始めたともされる。
仏飯とは違うため不必要である。
真宗系では用いない。
白米を山盛りにする理由は、高級な白米を大量に食べることができなかったため、「最後(死亡後)くらい白米を食べさせてあげよう」ということから。白米1合を普段使っているお釜とは別鍋で炊いて作る。
また茶碗1杯だけにする理由は「家を出て再び帰らぬ時は一膳の飯に限る」という習慣があった。嫁入りの際の家族との別れの食事はすべて一膳飯だった。
これは二(フタ)たび家へ帰らぬという意味であるとされる。
箸を立てる理由は「箸が刺さっていれば他の者が食べないから」「線香(大天香に見立て)を立てるから箸も立ててみた」「普段寝かしておく箸を立てる事により、(故人の魂に)死んだと理解させる」など不明。
1本だけ立てる理由も「縦は火、横は水。米は木。椀は土。と五行説から来たともされる。
また、椀の淵に寝かせれば十文字になるため、江戸時代の隠れキリスト教徒が始めたともされる。
仏飯とは違うため不必要である。
真宗系では用いない。
+神棚封じ
神は死を嫌うため神棚を閉じるとされている。
それと混同し、“仏壇も閉じる”と間違った事をする者もいる。
仏壇を閉じてしまうと、救いの手を差し伸べている仏に対し「結構です。お構いなく。」と言っているに等しい事になる。
仏教徒にとって神棚は不要である。
仏教徒であって、神道の氏子でもあるという事は、死後どちらの世界に行くつもりなのかも不明である。
どちらの宗教者からしても、中途半端な信仰心であり、どちらの世界にも行けない者ととらえられてもおかしくない。
それと混同し、“仏壇も閉じる”と間違った事をする者もいる。
仏壇を閉じてしまうと、救いの手を差し伸べている仏に対し「結構です。お構いなく。」と言っているに等しい事になる。
仏教徒にとって神棚は不要である。
仏教徒であって、神道の氏子でもあるという事は、死後どちらの世界に行くつもりなのかも不明である。
どちらの宗教者からしても、中途半端な信仰心であり、どちらの世界にも行けない者ととらえられてもおかしくない。
+北枕
お釈迦様が入滅した際の体の向きがもとに作られている。
正確には頭北面西であり、頭を北側にし、体は西側を向き横向きに肘を着いて寝ている状態である。
北枕は「普段寝る時に北枕にしていると縁起が悪い」「亡くなったら遺体は北枕にして安置する」とされている。
自宅の事情などで、北枕で安置する事は拘る必要が無い。
仏壇に足を向ける(本尊に足を向ける)事になるのであれば、逆に避けるべきである。
正確には頭北面西であり、頭を北側にし、体は西側を向き横向きに肘を着いて寝ている状態である。
北枕は「普段寝る時に北枕にしていると縁起が悪い」「亡くなったら遺体は北枕にして安置する」とされている。
自宅の事情などで、北枕で安置する事は拘る必要が無い。
仏壇に足を向ける(本尊に足を向ける)事になるのであれば、逆に避けるべきである。
+釘打ち
棺の蓋に釘を打ち、棺の蓋が開かなくすること。
現在でも、極稀に死亡と認定された後に生き返る事がある。
医療の発達していない昔では、そのような事は、妖怪やもののけの類である。その為、棺の蓋に釘を打ち棺を開けられなくした。
また、被差別部落の者を、生きたまま埋めるなどしていた時もこのようにして埋められていた。
いかに医療が発達し死亡の確認がはっきりとわかるとしても、釘打ちという行為は、現代には必要が無く、また存在してはいけない行為である。
現在でも、極稀に死亡と認定された後に生き返る事がある。
医療の発達していない昔では、そのような事は、妖怪やもののけの類である。その為、棺の蓋に釘を打ち棺を開けられなくした。
また、被差別部落の者を、生きたまま埋めるなどしていた時もこのようにして埋められていた。
いかに医療が発達し死亡の確認がはっきりとわかるとしても、釘打ちという行為は、現代には必要が無く、また存在してはいけない行為である。
+三途の川
葬頭川、正塚、三瀬川などと呼ばれている。
仏教が日本に伝わる前に中国で作られた偽教(ニセモノ)である。飛鳥時代頃に伝わり平安末期に広まった。
三途の川の名の由来は、「地獄道・餓鬼道・畜生道の三悪道から」と、「善人は金銀七宝の橋、軽い罪人は浅瀬、思い悪人は深く投げれの急な難所の三ヶ所から渡る」などとされている。
三途の川の河原では、親に先立って死んだ者は、親不孝の報いで石の塔を作るため石積みをさせられる。塔の完成寸前で鬼に壊されると言われている。
すべて、中国で生まれたニセモノの話であり、仏教徒は一切関係が無い。
仏教が日本に伝わる前に中国で作られた偽教(ニセモノ)である。飛鳥時代頃に伝わり平安末期に広まった。
三途の川の名の由来は、「地獄道・餓鬼道・畜生道の三悪道から」と、「善人は金銀七宝の橋、軽い罪人は浅瀬、思い悪人は深く投げれの急な難所の三ヶ所から渡る」などとされている。
三途の川の河原では、親に先立って死んだ者は、親不孝の報いで石の塔を作るため石積みをさせられる。塔の完成寸前で鬼に壊されると言われている。
すべて、中国で生まれたニセモノの話であり、仏教徒は一切関係が無い。
+順路変更
火葬場から自宅や寺院に戻る際、来た道とは違う道を使い帰る事。
「霊魂を家に連れて帰らないようにするため」に行う迷信。
仏教には霊魂は存在しない。
例え霊魂の類が存在するとしても、「自分の身内を迷子にして彷徨わせるのか?」「付いて来て欲しくないほど嫌いなら葬儀に出なければいい。」という話である。そして、お盆にお墓に行っても自分達で迷子にさせているのだから誰もいないはずである。
「霊魂を家に連れて帰らないようにするため」に行う迷信。
仏教には霊魂は存在しない。
例え霊魂の類が存在するとしても、「自分の身内を迷子にして彷徨わせるのか?」「付いて来て欲しくないほど嫌いなら葬儀に出なければいい。」という話である。そして、お盆にお墓に行っても自分達で迷子にさせているのだから誰もいないはずである。
+線香を絶やさない
「死んだばかりの遺体には魔が憑きやすいから、線香で魔を払うという」俗習である。
正確には死臭隠しである。遺体保管処置の技術が無い頃は線香で死臭を隠した。
「なぜ線香をずっと焚くのか?」と問われ「臭いから」と答えるわけにいかず広まった者と思われる。
線香の歴史は江戸中期からであり、日本仏教の歴史から見て、かなり浅いものである。
ほぼ全宗派で大きな法要には線香ではなく、沈香や伽羅などが用いられる。これらは高額であるが、線香は安価なで香りも悪く本堂で焚かれることはない。宗派によるが法要用の大天香などは通常の線香とは違う。
蝋燭も絶やさないとされるが、火事の原因であり危険である。実際にこれが原因の死亡事故も多い。
正確には死臭隠しである。遺体保管処置の技術が無い頃は線香で死臭を隠した。
「なぜ線香をずっと焚くのか?」と問われ「臭いから」と答えるわけにいかず広まった者と思われる。
線香の歴史は江戸中期からであり、日本仏教の歴史から見て、かなり浅いものである。
ほぼ全宗派で大きな法要には線香ではなく、沈香や伽羅などが用いられる。これらは高額であるが、線香は安価なで香りも悪く本堂で焚かれることはない。宗派によるが法要用の大天香などは通常の線香とは違う。
蝋燭も絶やさないとされるが、火事の原因であり危険である。実際にこれが原因の死亡事故も多い。
+茶碗割
一善飯を盛った、故人の茶碗を出棺後、火葬開始後、収骨後、還骨後などに、地面に叩きつけて割る事。
故人の使用していた茶碗を割る事で、霊魂として帰って来ても食べ物は用意できないといった事、遺品の廃棄に正当性を持たせる為、故人への恨みを込め叩きつける(茶碗割は嫁がやる事が多い)、茶碗割り以降、気持ちを割り切る」という言葉遊び…
など様々な理由が考えられる。
宗教的意味合いはなく、無意味である。
故人の使用していた茶碗を割る事で、霊魂として帰って来ても食べ物は用意できないといった事、遺品の廃棄に正当性を持たせる為、故人への恨みを込め叩きつける(茶碗割は嫁がやる事が多い)、茶碗割り以降、気持ちを割り切る」という言葉遊び…
など様々な理由が考えられる。
宗教的意味合いはなく、無意味である。
+友引(六曜)
友引に通夜をすると「友を引き込む(道ずれにされる)」という言葉遊びからの俗習。
六曜は中国で出来たもので、七曜(現在の曜日)や旬(10日毎の単位)と同じように作られたものである。
鎌倉末期か室町前期に伝わったとされており、現在では、陰陽道や民間信仰などが混ざり合い、名称(赤口以外)、解釈共にすべて変わっている。
現在広まった理由は、第二次世界大戦後の賭場で博打打(現在のヤクザ者に相当する者)がゲン担ぎ、縁起担ぎで行っていた物が広がった。
現在では、先勝→友引→先負→仏滅→泰安→赤口とあるが、本来は速喜(即吉)→共引(留引)→周吉(小吉)→虚亡(空亡)→泰安→赤口とされる。
友引の本来の意味は、継続、停滞を意味する。「良き事が起こるなら継続を、悪き事が起こるなら改善を…」と言うのが本来の“留引”である。
仏滅は、「物が一度滅し、新たに事が始まる」とも言われ、何かを始めるには泰安(大安)よりも良いとされる。現在の意味では「何事も遠慮し、病めば長引く。仏事はよろしい」とされており、結婚式も仏式でやれば良いとも取れる。
公共機関のカレンダーには掲載を取りやめる行政指導が行われている。
仏滅など仏教に関連性がありそうな言葉が使われているが、陰陽道や、中国の民間信仰などに由来しており、仏教に関連性は一切ない。
ちなみに、お釈迦さまは占いを禁じている。真宗系でも一切気にすることはしない。
六曜は中国で出来たもので、七曜(現在の曜日)や旬(10日毎の単位)と同じように作られたものである。
鎌倉末期か室町前期に伝わったとされており、現在では、陰陽道や民間信仰などが混ざり合い、名称(赤口以外)、解釈共にすべて変わっている。
現在広まった理由は、第二次世界大戦後の賭場で博打打(現在のヤクザ者に相当する者)がゲン担ぎ、縁起担ぎで行っていた物が広がった。
現在では、先勝→友引→先負→仏滅→泰安→赤口とあるが、本来は速喜(即吉)→共引(留引)→周吉(小吉)→虚亡(空亡)→泰安→赤口とされる。
友引の本来の意味は、継続、停滞を意味する。「良き事が起こるなら継続を、悪き事が起こるなら改善を…」と言うのが本来の“留引”である。
仏滅は、「物が一度滅し、新たに事が始まる」とも言われ、何かを始めるには泰安(大安)よりも良いとされる。現在の意味では「何事も遠慮し、病めば長引く。仏事はよろしい」とされており、結婚式も仏式でやれば良いとも取れる。
公共機関のカレンダーには掲載を取りやめる行政指導が行われている。
仏滅など仏教に関連性がありそうな言葉が使われているが、陰陽道や、中国の民間信仰などに由来しており、仏教に関連性は一切ない。
ちなみに、お釈迦さまは占いを禁じている。真宗系でも一切気にすることはしない。
+箸渡し(二人収骨)
食べ物を二人で同時に掴むこと、または、箸から箸へ渡す事を、“箸渡し・拾い箸(合わせ箸)”と言い嫌い箸、忌み箸とされている。
これはお骨を同じ動作で拾う事からである。
お骨を二人で拾うのは「三途の川の橋渡し」と箸渡しを使った言葉遊びである。
三途の川は仏教に関係のない俗習であり、箸渡しも俗習から生まれた俗習である。
行う必要はない。真宗系では絶対に行わない。
これはお骨を同じ動作で拾う事からである。
お骨を二人で拾うのは「三途の川の橋渡し」と箸渡しを使った言葉遊びである。
三途の川は仏教に関係のない俗習であり、箸渡しも俗習から生まれた俗習である。
行う必要はない。真宗系では絶対に行わない。
+棺回し
釘打ちと同じように出棺前に行われる。
式場内で棺をグルグルと回したり、自宅や式場の周りをグルグルと回る事。
自宅の周りを回る事を、「近所の人への最後の挨拶や、愛用した自宅だから…」と回すのであれば構わないのかも知れない。
棺回しが生まれた理由は、火葬場(墓場)に行く前に棺をグルグルと回し、方向感覚を無くさせ、霊魂となって家に帰れなくするというものである。また、誰が釘打ちをしたのかなどを故人に分からせなくさせ、憑りつかれる事を防ぐことである。
俗習であり行う必要が無い。
式場内で棺をグルグルと回したり、自宅や式場の周りをグルグルと回る事。
自宅の周りを回る事を、「近所の人への最後の挨拶や、愛用した自宅だから…」と回すのであれば構わないのかも知れない。
棺回しが生まれた理由は、火葬場(墓場)に行く前に棺をグルグルと回し、方向感覚を無くさせ、霊魂となって家に帰れなくするというものである。また、誰が釘打ちをしたのかなどを故人に分からせなくさせ、憑りつかれる事を防ぐことである。
俗習であり行う必要が無い。
+仏壇の向き
仏壇を安置する場所(方角)、向き(方向)について、吉兆を気にする事。
家の鬼門を避け、西側に置き、東を向かせる事が正しいとされるが、一概に正しいとは言えない。
「鬼門とは風水に基づいて…」となっているが風水は占いであり仏教と関係が無い。お釈迦様は占いを禁じている。
また日本で鬼門は北西とされているが、これは京都から見て北西に蝦夷と言われる朝廷に従わない部族がいた事である。蝦夷を鬼とし迫害した事であり、童話の「桃太郎」は鬼を討つがこれは蝦夷討伐をモデルにしているともされる。現在の東北地方の人達を差別していることになりうる。
西側に置く事も、宗派により異なる。
しかし、仏壇の御本尊が方角の基準時なり、我々が基準ではない為、本来は気にすることはない。
現に、古い寺院では方角を気にしていない場合もある、(埋立以前の)海沿いの古い寺院では、海に背を向け本堂が立てられている場合もある。これは本堂内に潮風が当たる事を避けたためである。
家の鬼門を避け、西側に置き、東を向かせる事が正しいとされるが、一概に正しいとは言えない。
「鬼門とは風水に基づいて…」となっているが風水は占いであり仏教と関係が無い。お釈迦様は占いを禁じている。
また日本で鬼門は北西とされているが、これは京都から見て北西に蝦夷と言われる朝廷に従わない部族がいた事である。蝦夷を鬼とし迫害した事であり、童話の「桃太郎」は鬼を討つがこれは蝦夷討伐をモデルにしているともされる。現在の東北地方の人達を差別していることになりうる。
西側に置く事も、宗派により異なる。
しかし、仏壇の御本尊が方角の基準時なり、我々が基準ではない為、本来は気にすることはない。
現に、古い寺院では方角を気にしていない場合もある、(埋立以前の)海沿いの古い寺院では、海に背を向け本堂が立てられている場合もある。これは本堂内に潮風が当たる事を避けたためである。
+枕刀(守り刀)
刀は武士の精神とされ、寝る時も刀を身から離すことが無かった。
死亡時(討死・切腹・斬首などは除く)も、通常寝るときと同じように置かれた。こらが由来とされ現在に至る。
人を殺める事を生業としている武士にとって怨霊に襲われる可能性がありそれを破るため。または、魔を寄付けない為。
猫を魔の化身(化け猫)と考えられており、猫が光り物を嫌うためなどがある。
魔という考え方や、お守りの類であり仏教とは関係が無い。
死亡時(討死・切腹・斬首などは除く)も、通常寝るときと同じように置かれた。こらが由来とされ現在に至る。
人を殺める事を生業としている武士にとって怨霊に襲われる可能性がありそれを破るため。または、魔を寄付けない為。
猫を魔の化身(化け猫)と考えられており、猫が光り物を嫌うためなどがある。
魔という考え方や、お守りの類であり仏教とは関係が無い。
+門燈
字の通り自宅や門の門前に置く灯りである。
昔、親類が遠方から駆け付ける際、夜中になる事が多く、また街灯も無かった為、見ず知らずの土地に来てもす、ぐに自宅が解るように置いた物である
現在では、雰囲気作りや、式場の隙間隠しなどに用いられ、葬儀社のオプションプラン(追加料金の発生する物)に使われている。
自宅や、寺院の木造の門前に置くのであれば厳かな雰囲気がえられる。室内には必要が無い。
昔、親類が遠方から駆け付ける際、夜中になる事が多く、また街灯も無かった為、見ず知らずの土地に来てもす、ぐに自宅が解るように置いた物である
現在では、雰囲気作りや、式場の隙間隠しなどに用いられ、葬儀社のオプションプラン(追加料金の発生する物)に使われている。
自宅や、寺院の木造の門前に置くのであれば厳かな雰囲気がえられる。室内には必要が無い。
+冥土・冥途
冥土・冥途・冥界・冥府はすべて、仏教から見て、基本的に異教徒の「地獄」を指す。
中国で生まれた言葉であり道教の霊が行く世界である。また日本神話、古神道、神道でも用いられている。
“冥”という字には、「うかがい知れない何か」「暗くてよく(はっきり)見えない」「黒くくすんでいる」という意味がある。
“冥途”の訓読みは“冥き途(くらきみち)”であり、「煩悩に迷う世界」「死者が迷っていく道」であり、六道につながる。
宗派により本尊の違いから名称が異なり、西方極楽浄土、霊山浄土、東方妙喜世界、東方浄瑠璃世界、無勝荘厳国、蓮華蔵世界などがあるが、これらを浄土、浄国、浄界と言う。宗派により異なる理由は、各宗派の本尊の持つ、浄土を目指すのである。
したがって、「“浄土”に生まれ変われていない=六道にいる=地獄道にも行く=地獄堕ち」となる。
テレビやラジオなどで、著名人の訃報を伝える際、天国=キリスト教、浄土=仏教、神道=黄泉国などのイメージがあり、特定の宗教の言葉を避けるため用いられた。
中国で生まれた言葉であり道教の霊が行く世界である。また日本神話、古神道、神道でも用いられている。
“冥”という字には、「うかがい知れない何か」「暗くてよく(はっきり)見えない」「黒くくすんでいる」という意味がある。
“冥途”の訓読みは“冥き途(くらきみち)”であり、「煩悩に迷う世界」「死者が迷っていく道」であり、六道につながる。
宗派により本尊の違いから名称が異なり、西方極楽浄土、霊山浄土、東方妙喜世界、東方浄瑠璃世界、無勝荘厳国、蓮華蔵世界などがあるが、これらを浄土、浄国、浄界と言う。宗派により異なる理由は、各宗派の本尊の持つ、浄土を目指すのである。
したがって、「“浄土”に生まれ変われていない=六道にいる=地獄道にも行く=地獄堕ち」となる。
テレビやラジオなどで、著名人の訃報を伝える際、天国=キリスト教、浄土=仏教、神道=黄泉国などのイメージがあり、特定の宗教の言葉を避けるため用いられた。
+冥福(をお祈りします)
「冥土・冥途・冥界・冥府での幸福」を指す言葉である。道教や仏教徒の民間信仰内で使われる。
上記の“冥土・冥途”にあるように、冥土は地獄の違う言い方と言うだけであり、「冥福をお祈りします」とは「地獄でお幸せに…」に等しく避けるべき言葉である。
真宗系では、不適切な言葉であり絶対に用いない。代わりの言葉として「こころより哀悼の意を表します」などがある。
キリスト教でも用いず、プロテスタントは死後確実に天国にいる。カトリックでは死後の世界は存在しない。
「冥福を…」と使う事は、悪魔に魂を縛られている、または無にされた(存在を消された)状態につながる為、避けるべきである。
上記の“冥土・冥途”にあるように、冥土は地獄の違う言い方と言うだけであり、「冥福をお祈りします」とは「地獄でお幸せに…」に等しく避けるべき言葉である。
真宗系では、不適切な言葉であり絶対に用いない。代わりの言葉として「こころより哀悼の意を表します」などがある。
キリスト教でも用いず、プロテスタントは死後確実に天国にいる。カトリックでは死後の世界は存在しない。
「冥福を…」と使う事は、悪魔に魂を縛られている、または無にされた(存在を消された)状態につながる為、避けるべきである。
+霊魂
生命や精神の源とされる存在。
仏教では、現在の俗に言う霊魂の概念はない。(自他平等の境地を目指す思想とされ、全く別のものである)
中国の道教や古神道、神道で用いられる。
道教では、精神に魂、肉体に魄(はく)が宿っているとされ、死後、魂は天に魄は地に帰るとされている。有名な中国映画の「キョンシー」は魂が天に帰したが体(魄)が残った状態とされる。
神道では死後、神のもとに帰るとされている。優れた実績を残したものは尊と同等の神格を持つとされる。一般人でも第二次世界大戦中の戦死者は「英霊」とされ敬意を表された。霊と魂の差は曖昧であり、区別や分類は不明である。
荒魂。和魂とは神が「災いをもたらすか、福をもたらすか」の違いであるが、どちらも神であり違いはない。
また「霊位」は無宗教葬、や創価学会が用いる。
仏教では、現在の俗に言う霊魂の概念はない。(自他平等の境地を目指す思想とされ、全く別のものである)
中国の道教や古神道、神道で用いられる。
道教では、精神に魂、肉体に魄(はく)が宿っているとされ、死後、魂は天に魄は地に帰るとされている。有名な中国映画の「キョンシー」は魂が天に帰したが体(魄)が残った状態とされる。
神道では死後、神のもとに帰るとされている。優れた実績を残したものは尊と同等の神格を持つとされる。一般人でも第二次世界大戦中の戦死者は「英霊」とされ敬意を表された。霊と魂の差は曖昧であり、区別や分類は不明である。
荒魂。和魂とは神が「災いをもたらすか、福をもたらすか」の違いであるが、どちらも神であり違いはない。
また「霊位」は無宗教葬、や創価学会が用いる。
現在では神社で行われることが多い。
男の子の3歳と5歳、女の子の3歳と7歳に行われる。(地方によっては男女、年齢が異なる)
昔は病気が多く、子供が早くに亡くなる事が多く、七五三の年齢まで無事生きていれば大丈夫とされていた。
旧暦の11月(収穫直後)の満月の夜(鬼が出歩かない日)に氏神に収穫の感謝と子供の成長を祝って行った。
と言う建前である。
実際のところは、口減らしと子供の間引きである。
「不作で収穫量が減れば食べていけない」「七五三の年齢までいけば障害児かどうかの判別がつく」などがある。
その為、神社へ行き「子供を神様の元へお返しする」「神隠しにあった」などを理由にし、「子供を捨てる」「遊郭へ売る」「(生贄とし)殺害する」などが行われていた。
現在と違い罪悪感は皆無である。現在でも言われている「7歳までは神の子」には続きの考え方があり「あの世とこの世の中間に居る者」であり、「すぐに神にお返しできる」とされていたことが理由である。
男の子の3歳と5歳、女の子の3歳と7歳に行われる。(地方によっては男女、年齢が異なる)
昔は病気が多く、子供が早くに亡くなる事が多く、七五三の年齢まで無事生きていれば大丈夫とされていた。
旧暦の11月(収穫直後)の満月の夜(鬼が出歩かない日)に氏神に収穫の感謝と子供の成長を祝って行った。
と言う建前である。
実際のところは、口減らしと子供の間引きである。
「不作で収穫量が減れば食べていけない」「七五三の年齢までいけば障害児かどうかの判別がつく」などがある。
その為、神社へ行き「子供を神様の元へお返しする」「神隠しにあった」などを理由にし、「子供を捨てる」「遊郭へ売る」「(生贄とし)殺害する」などが行われていた。
現在と違い罪悪感は皆無である。現在でも言われている「7歳までは神の子」には続きの考え方があり「あの世とこの世の中間に居る者」であり、「すぐに神にお返しできる」とされていたことが理由である。